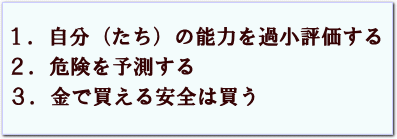2009年12月18日、冬の富士山登山を行っていた、元F1レーサーの片山右京さんら3人が遭難しました。ニュースや新聞でも大々的に取り上げられたので、事故の経過については説明しませんが・・・。
この遭難について、野口健さんが自身のブログで言及していますが、私の考えも基本的に同じです。
冬富士は夏と全く様相が違い、非常に気象条件の厳しい山になります。私も経験がありますが、体が浮き上がるほどの烈風、極低温。足元もカリカリのアイスバーン状態になり、技術的には(ヒマラヤ登山を目指す人にとっては)それほど高度ではありませんが、僅かなミスが死に直結する山に一変します。
しかし片山さんは7大陸最高峰登頂を目指し、南極のビンソンマッシフ峰への遠征を控えていたわけで、そのトレーニングとして冬の富士山に登るのは、理に適った行動です。もし南極のブリサード対策に、寒波が襲来中で天候が荒れることを承知で敢えて行ったのなら、それは誰にも非はない遭難、ということです。
強い寒波が来て天候が荒れることをわかっていて登山を行ったか・・・そこがはっきりしていないので、最終的な判断はできないのですが・・・。
寝ているときにテントごと吹き飛ばされたわけですから、遭難の原因は技術が未熟だったわけでも、装備がしっかりしていなかったわけでもありません。登山届けを出していなかった点はいただけませんが、よくある無謀登山とは違います。
片山さんが仲間をおいて下山した事についていろいろ言う人がいるようですが、あの状況では当然の行動、ベストの選択だったと思います。
この遭難について、野口健さんが自身のブログで言及していますが、私の考えも基本的に同じです。
冬富士は夏と全く様相が違い、非常に気象条件の厳しい山になります。私も経験がありますが、体が浮き上がるほどの烈風、極低温。足元もカリカリのアイスバーン状態になり、技術的には(ヒマラヤ登山を目指す人にとっては)それほど高度ではありませんが、僅かなミスが死に直結する山に一変します。
しかし片山さんは7大陸最高峰登頂を目指し、南極のビンソンマッシフ峰への遠征を控えていたわけで、そのトレーニングとして冬の富士山に登るのは、理に適った行動です。もし南極のブリサード対策に、寒波が襲来中で天候が荒れることを承知で敢えて行ったのなら、それは誰にも非はない遭難、ということです。
強い寒波が来て天候が荒れることをわかっていて登山を行ったか・・・そこがはっきりしていないので、最終的な判断はできないのですが・・・。
寝ているときにテントごと吹き飛ばされたわけですから、遭難の原因は技術が未熟だったわけでも、装備がしっかりしていなかったわけでもありません。登山届けを出していなかった点はいただけませんが、よくある無謀登山とは違います。
片山さんが仲間をおいて下山した事についていろいろ言う人がいるようですが、あの状況では当然の行動、ベストの選択だったと思います。